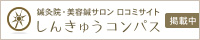今回は、一般的な自律神経の考え方との比較から、ポリヴェーガル理論の特徴について簡単にまとめたいと思います。
まずは一般的な自律神経の考え方について簡単にまとめてみます。
・交感神経と副交感神経の2つに分けられる。
・交感神経が優位の時は副交感神経は抑制され、副交感神経が優位の時は交感神経が抑制される(拮抗支配)。
・交感神経と副交感神経が、シーソーのようにバランスを取り合っている。
・交感神経は活動時に働き、副交感神経は休息時に働く。
・ストレスがあると交感神経が優位になり、リラックスすると副交感神経が優位になる。
ネットやメディア等で自律神経について説明しているのを見ると、おおよそ上記のようなものであるように思います。
このような見方はもちろん間違っているわけではなく、ある一面では正しいと言えるでしょう。
従来の考え方に比して、ポリヴェーガル理論では自律神経を次のようにとらえます。
・腹側迷走神経と交感神経と背側迷走神経の3つに分けられる。(従来は2つ)
・3つの自律神経は古いものから新しいものへ、進化の過程で階層的に発達した。(従来にはない)
・腹側迷走神経が優位の時は交感神経と背側迷走神経は穏やかに働き、「健康・成長・回復」を促進する。(シーソーの関係だけではない)
・ストレスに対する防衛反応として、交感神経(可動化)と背側迷走神経(不動化)の2つがある。(従来は交感神経を強調)
・防衛反応として交感神経や背側迷走神経が働くときは、腹側迷走神経は抑制され、「健康・成長・回復」が妨げられる。(副交感神経の働きをより細分化)
ポリヴェーガル理論という自律神経の新しい見方により、従来とは異なった一面を持つ自律神経の働きが見えてきます。
「現代人は交感神経が優位になりがちだから、副交感神経を優位にするよう心がけましょう」という話をとてもよく見聞きします。決して間違いではありませんが、自律神経の不調は必ずしも交感神経によるものだけとは限りません。副交感神経の1つである背側迷走神経も、第2の防衛反応(不動化・シャットダウン)として存在するのです。
ポリヴェーガル理論を踏まえたうえで、自律神経の働きを整えるにはどうしたらよいのでしょうか。また私たちの「健康・成長・回復」を促進するためには何が必要なのでしょうか。
もうこれまでの説明でだいたい予想がつくかもしれませんが、それは
「腹側迷走神経を優位な状態に保つこと(戻すこと)」
と言うことができるでしょう。
(つづく)
参考文献
・ポリヴェーガル理論入門(ステファン・W・ポージェス著/春秋社)
・セラピーのためのポリヴェーガル理論(デブ・デイナ著/春秋社)
・その生きづらさ、発達性トラウマ?(花丘ちぐさ著/春秋社)
・ポリヴェーガル理論 臨床応用大全(ステファン・W・ポージェス、デブ・デイナ編著/春秋社)
湘南さがみはりきゅうマッサージ
【自律神経とメンタルヘルスの鍼灸院】
(神奈川県伊勢原市・厚木市・秦野市・平塚市他近隣地域)